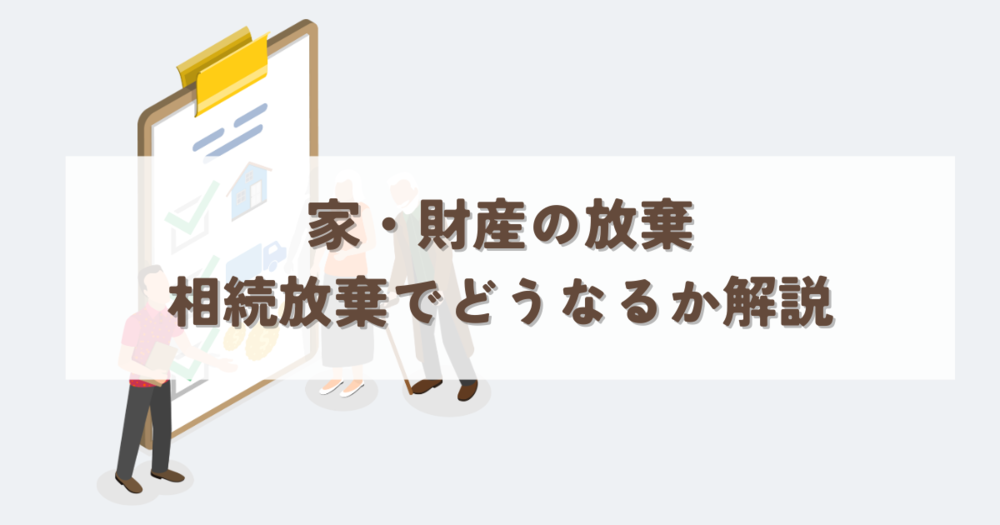
特に、老朽化した家屋や多額の負債を抱える不動産を相続した場合、その対応に頭を悩ませる方も少なくないでしょう。
この状況下で、財産放棄という選択肢を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続放棄は、複雑な手続きや様々なリスクを伴うため、十分な理解と準備が必要です。
今回は、財産放棄を検討されている方が抱える疑問を解決できるよう、家の扱いについて分かりやすく解説します。
相続放棄によって何が起こるのか、具体的な手続き、そして放棄前に検討すべき点などを、順を追ってご紹介します。
家と財産、すべてを放棄するとどうなる?
相続放棄とは何か
相続放棄とは、被相続人が亡くなった際に残された全ての財産に関する権利を放棄することです。
プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も全て相続しないことを意味します。
そのため、「家だけを放棄する」といったことはできません。
相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
この3ヶ月間は熟慮期間と呼ばれ、相続放棄の可否を慎重に検討する期間です。
相続放棄で家がどうなるのかパターン別解説
・他の相続人がいる場合:他の相続人が相続を承継します。
相続人の順位は法律で定められており、第一順位相続人が放棄すれば第二順位、第二順位が放棄すれば第三順位へと相続権が移行します。
・相続人全員が放棄した場合:誰も相続を承継しないため、家は最終的に国庫に帰属します。
ただし、相続財産清算人が選任され、家の売却や解体などの手続きが行われます。
相続人全員が放棄した場合の注意点
相続人全員が放棄した場合、家は国庫に帰属する前に、相続財産清算人が選任されます。
相続財産清算人は、家の売却や解体を行い、債権者への債務返済などを執り行います。
相続財産清算人を選任するには家庭裁判所への申立てが必要で、費用も発生します。
また、相続放棄をしても、相続開始時点においてその家に住んでいた場合は、新たな相続人や相続財産清算人が管理を始めるまで、家の保存義務を負う場合があります。
これは、家の状態を維持し、近隣住民に迷惑をかけないよう適切な管理を行う義務です。
保存義務を怠ると、損害賠償請求をされる可能性もあります。
保存義務と管理責任について
相続放棄後も、相続開始時点でその家に住んでいた場合は、新たな相続人や相続財産清算人が管理を始めるまで、家の保存義務を負います。
これは、家の状態を維持し、近隣住民に迷惑をかけないよう適切な管理を行う義務です。
具体的な内容としては、簡単な修繕、庭木の剪定、害虫駆除などがあげられます。
保存義務を怠ると、建物の倒壊や火災などによる近隣への損害賠償責任を負う可能性があります。
財産放棄後の家の処分の方法
相続人全員が相続放棄した場合、相続財産清算人が家の処分を行います。
通常は、競売などを通して現金化し、債権者への弁済やその他の費用に充当されます。
場合によっては、解体費用が必要となることもあります。
相続放棄前に検討すべきこと
相続放棄は、一度行うと取り消すことができません。
そのため、相続放棄をする前に、以下の点を十分に検討することが重要です。
・家を残す必要性:本当に家を相続する必要がないか。
・負債の状況:家の他に負債がないか、ある場合その額はどのくらいか。
・他の相続人の意向:他の相続人はどのような考えを持っているか。
・家の売却可能性:家を売却することで債務を解消できる可能性はあるか。

財産放棄 家 具体的な手続きと必要な費用
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の手続きは、家庭裁判所への申立てによって行われます。
まず、相続開始を知った日から3ヶ月以内に、相続放棄の申述書を提出する必要があります。
申述書には、相続人の戸籍謄本や被相続人の死亡診断書などの書類を添付する必要があります。
家庭裁判所は、申立て内容を審査し、相続放棄を認めるか否かを決定します。
家庭裁判所への申立に必要な書類と費用
家庭裁判所への申立てには、相続人の戸籍謄本、被相続人の死亡診断書、相続財産目録などが必要となります。
また、収入印紙などの費用も必要です。
具体的な費用は、裁判所によって異なる場合があります。
相続財産清算人選任の申立て
相続人全員が相続放棄した場合、相続財産清算人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
相続財産清算人は、家の売却や解体など、相続財産の処理を行います。
相続財産清算人の選任申立てには、費用が発生します。
弁護士への相談を検討するメリット
相続放棄は複雑な手続きを伴うため、弁護士に相談することで、手続きの進め方やリスクなどを理解し、スムーズに手続きを進めることができます。
弁護士は、相続放棄に関する専門的な知識を持っており、適切なアドバイスをしてくれます。
よくある質問と回答
・借地権の場合:借地権も相続放棄の対象となります。
・滞納家賃:相続放棄後は、滞納家賃の支払義務はなくなります。
・配偶者:配偶者には、一定期間住み続ける権利(配偶者短期居住権)が認められる場合があります。

まとめ
財産放棄、特に家の相続放棄は、複雑な手続きと様々なリスクを伴います。
相続放棄によって家は最終的に国庫に帰属しますが、その前に相続財産清算人が選任され、家の処分が行われます。
また、相続放棄後も保存義務や管理責任を負う可能性がある点に注意が必要です。
相続放棄を検討する際は、熟慮期間中に弁護士などの専門家に相談し、状況を的確に把握した上で、後悔のない選択をすることが重要です。
手続きには費用が発生し、複雑なため、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。
ご自身の状況に合わせた最善の策を検討し、安心して相続手続きを進めましょう。












